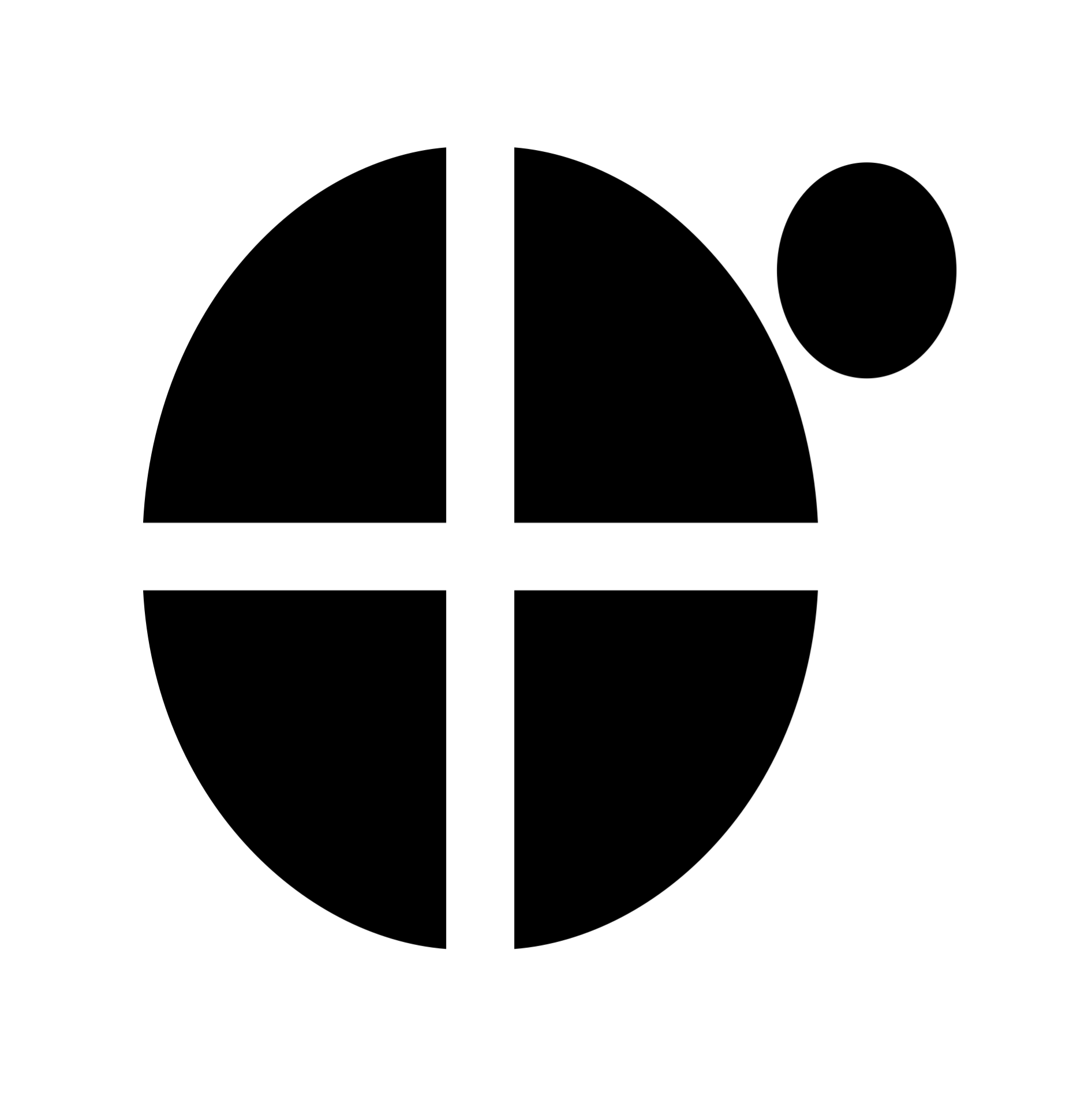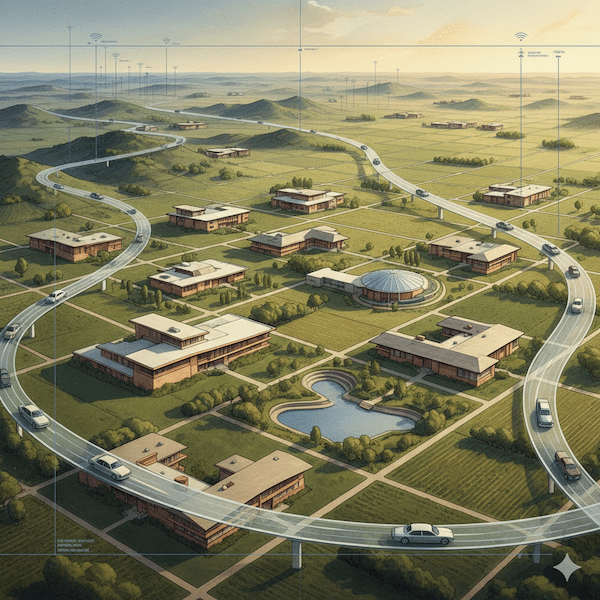〜縮小社会における持続可能な都市モデル「ネオ・ローマン・モデル」の可能性〜
※本記事は、北海道庁の道路現況調査(令和5年度)および古代ローマ史・防災工学の知見を基に構成しています。
「都市とは、石と煉瓦の集積ではなく、そこに住む人々の意思である」
かつて聖アウグスティヌスが残したこの言葉は、都市の精神性を説いたものですが、現実の都市を物理的に支えているのは、紛れもなく「インフラストラクチャー(下部構造)」という冷徹な工学的事実です。そして、その大地がひとたび牙を剥けば、人々の意思がいかに強固であろうとも、脆いインフラは瞬時に崩壊し、都市機能は麻痺します。
古代ローマ帝国は、しばしばその軍事的な征服劇や政治的なドラマによって語られますが、現代の都市工学的視点から再評価すべき真の姿は、驚異的な規模と精度で構築された「インフラ国家」としての側面です。彼らは領土を単に占領するのではなく、そこに水を供給し、排水を処理し、物資を輸送するシステムを埋め込むことで、「ローマの秩序(Ordo)」を物理的に刻印しました。特筆すべきは、ポンペイの悲劇に見られるような火山リスクを抱えるイタリア半島において、彼らが「壊れない(あるいは直しやすい)」インフラを志向していた点です。
翻って、現代の日本。とりわけ明治以降、原生林を切り開き急速にインフラを拡張してきた北海道は今、重大な歴史的岐路に立たされています。人口減少と施設の老朽化が同時に進行する中で、私たちはかつてのような「無限の拡大」を維持することはもはや不可能です。さらに、洞爺湖町においては、20年から30年周期で噴火を繰り返す有珠山という「地球の脈動」と共に生きる覚悟が問われています。
本稿では、2000年の時を超えて機能し続けるローマの工学的遺産と、北海道・洞爺湖町の現状データ、そして不可避な地殻変動リスクを徹底的に比較分析します。そこから浮かび上がるのは、縮小社会において豊かさと安全を維持するための、新たな「都市の工学」の輪郭です。
1. ローマ都市計画の工学的基盤:カストルムとグリッドの功罪
秩序を刻印する「カストルム」の論理
ローマの都市計画は、美学的な要請よりも、極めて実利的な軍事的規律の結晶として誕生しました。その起源は、ローマ軍団が遠征先で設営した野営地「カストルム(Castrum)」にあります。
彼らは未知の土地や敵対的な環境において、まず南北軸である「カルド・マクシムス(Cardo Maximus)」と、東西軸である「デクマヌス・マクシムス(Decumanus Maximus)」という二本の主要道路を直交させることから始めました。この交差点(グロマ)は都市のへそとされ、そこに行政・経済・宗教の中枢機能である「フォルム(Forum)」が設置されたのです。
この厳格な直交格子(グリッド)システムは、単なる区画整理の手法にとどまりません。帝国のどこにいてもローマ市民が同一の空間感覚と利便性を享受できることを保証する、「標準化(Standardization)」の装置として機能しました。しかし、さらに重要なのは、このグリッドが「迅速な部隊展開」を可能にする軍事インフラであったという点です。これは現代的に言えば、災害時の「迅速な避難路・救援路」の確保と同義です。
北海道におけるグリッドの移植と環境・災害のパラドックス
一方、このローマ的思考は、19世紀の北海道開拓にも色濃く反映されています。札幌をはじめとする北海道の主要都市に見られる碁盤の目は、明治政府が招聘したアメリカ人顧問ホーレス・ケプロンらの助言による「アメリカ式グリッド」の導入ですが、その本質はローマと同様、原生林という「カオス」に、統治可能な「秩序」を強制的に上書きする行為でした。
しかし、地中海世界で機能したシステムが、北国の風土、とりわけ火山と雪が共存する洞爺湖周辺の環境に完全に適合するわけではありません。以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | 【古代ローマ帝国】 (地中海性気候・地震帯) | 【現代北海道・洞爺湖】 (亜寒帯湿潤・活火山帯) |
|---|---|---|
| グリッドの主目的 | 軍事的規律・統治の可視化 および部隊の緊急展開 | 土地の商品化(不動産区分) および効率的な入植 |
| 気候・災害への適応 | 直線道路が風を通し 都市の熱を逃がす(冷却効果) | 直線道路が強風の通り道となり 地吹雪を誘発 / 噴火時の避難路確保 |
| インフラの冗長性 | 複数の水道橋による バックアップ体制(リスク分散) | 単一ライフラインへの依存 災害時の断絶リスクが高い |
特筆すべきは「地殻変動への対応」です。2000年の有珠山噴火では、国道230号線が地盤隆起によって階段状に破壊されました。ローマのグリッドは「面的な支配」には有効ですが、地形そのものが変形する局面においては、硬直的なグリッド構造が逆に復旧を妨げる可能性も孕んでいます。「涼」を呼ぶための直線道路が、北海道では猛烈な地吹雪の「風の回廊」となるように、技術の移植には「気候風土(Climate)」と「地質リスク(Geology)」という変数が不可欠なのです。
2. インフラの耐久性と経済性:重力 vs 電力 vs 変動力
ローマの街道:1000年を見据えた多層構造の強靭さ
現代の道路工学と比較した際、ローマ街道(Viae Romanae)の特異性は、その圧倒的な「過剰品質」にあります。現代のアスファルト舗装が表層・基層合わせて20〜30cm程度であるのに対し、ローマの主要幹線道路は総厚1メートルを超えることも珍しくありませんでした。
彼らは地面を深く掘り下げ、最下層に「スタメン(Statumen)」と呼ばれる大きな石を敷き詰め、その上に粘土や砂利の「ルダス(Rudus)」、さらに細かい砕石の「ヌクレウス(Nucleus)」、そして最上層に多角形の平らな敷石「スムマ・クルスタ(Summa Crusta)」を隙間なく噛み合わせるという、堅牢な四層構造(Agger)を採用しました。
この重厚な構造は、平時においてはメンテナンスフリーを実現し、有事(軍事行動や災害)においては、たとえ表層が損傷しても路盤自体は機能を維持できるという「レジリエンス(回復力)」を担保していました。
道路インフラの設計耐久年数と災害耐性の比較
※アスファルトは柔軟性があるが、大規模な地殻変動には路盤ごと崩壊するリスクがある。
火山地帯における「水」と「熱」のエネルギー論
水インフラに関しても、両者のアプローチは示唆に富んでいます。
ローマの水道橋は、平均して約0.1%という極めて緩やかな勾配を維持し、外部動力を用いずに「重力ポテンシャル」のみで水を輸送し続けました。これは停電が存在しないシステムであり、災害時にも水が流れ続ける可能性が高いことを意味します。
対して、現代日本の水道システムは、ポンプによる加圧に膨大な電力を消費しています。洞爺湖町のような火山地帯では、噴火に伴う停電リスクは常に付きまといます。電力が止まれば水も止まる現代のシステムは、ローマ式に比べて災害脆弱性が高いと言わざるを得ません。
しかし、洞爺湖にはローマにはない強力なエネルギー源があります。それが「地熱(温泉)」です。ローマ人が重力を利用したように、洞爺湖町は足元にある熱エネルギーを、除雪(ロードヒーティング)や給湯の動力として「パッシブ(受動的)」に利用するシステムへと転換することができれば、外部電力への依存度を下げ、災害時の自律性を高めることが可能です。
3. インフラの「ポンジ・スキーム化」と地質リスクの二重苦
高度経済成長期、日本は「道路を作れば街が発展し、税収が増える」という前提の下、郊外へと都市を拡張し続けました。北海道における道路実延長(供用延長)は約9万775km(令和5年度)に達し、これは地球を2周以上する長さに相当します。
新規開発が生む一時的なキャッシュフローで、古いインフラの維持費を賄うという構造は、ある種の「自転車操業」によって成立していたのです。
しかし、人口減少期に入り、このサイクルは逆回転を始めました。これを都市計画の文脈では「成長のポンジ・スキーム(Ponzi Scheme)」と呼びますが、洞爺湖町の場合はさらに深刻です。
インフラの老朽化に加え、周期的な地殻変動による破壊リスクが加算されるからです。「直してもまた壊れるかもしれない」土地において、低密度のまま拡散した市街地をすべて維持することは、財政的に破綻への道を歩むことと同義なのです。
人口密度と行政コストの相関:リスク係数の加算
国土交通省の調査によれば、DID(人口集中地区)の人口密度が低下すると、一人当たりの行政コストは指数関数的に上昇することが示されています。下図は、拡散した都市がいかに非効率であり、災害復旧において不利であるかを視覚化したものです。
人口密度低下に伴う1人当たりコストの増大イメージ
高密度
(コンパクト)
標準的
地方都市
3倍以上
低密度・拡散
(高リスク)
※インフラ維持・除雪・災害復旧等のコスト総計概念図
4. 洞爺湖町における具体的展望:ネオ・ローマン・モデルの実装
では、これらの歴史的・定量的分析、そして「変動する大地」という前提を踏まえ、洞爺湖町のような自治体はどのような戦略を採るべきでしょうか。古代ローマの叡智を現代的、かつ火山地帯向けに再解釈した「ネオ・ローマン・モデル」を提案します。
① 「ゾーニング」によるリスクとコストの分離
ローマの都市が城壁の内と外を明確に分けたように、現代の洞爺湖町も「守り抜く領域」と「自然に委ねる領域」を明確にゾーニングする必要があります。
- コア・ゾーン(高密度・高耐久): 虻田地区の中心部(役場周辺)など、比較的リスクがコントロールしやすく、経済活動が集中するエリア。ここにはローマ街道のような「高耐久インフラ」と「無電柱化・共同溝」を集中投資し、噴火時でも機能維持できる拠点とする。
- バッファ・ゾーン(低密度・可変性): 火口に近いエリアや断層直上。ここは「壊れることを前提」とした安価で復旧容易なインフラ(木道や簡易舗装など)を採用し、居住を制限する。ローマが氾濫原を建築不可としたような「撤退の勇気」を持つ。
② インフラ・メンテナンスの「公私連携(エウエルゲティズム)」
ローマ帝国において、公共建築やインフラの多くは、皇帝や富裕な市民(Euergetes)による私財の寄付によって建設・維持されました。現代において、税収のみですべてのインフラを維持・更新することは不可能です。
- ● 目的税としての入湯税・宿泊税の明確化: 観光客から徴収する税を、一般財源として埋没させるのではなく、「防災・景観維持・インフラ更新」のための特定財源として可視化し、受益者負担の原則を強化する。
- ● インフラツーリズム(変動する大地の博物館): 2000年の有珠山噴火遺構(金比羅火口など)は、破壊されたインフラそのものが観光資源です。ローマの廃墟が人を呼ぶように、「自然の力で破壊された道」を保存・展示し、その収益を「生きている道」の維持費へ還流させる循環モデルを構築する。
- ● 企業版ふるさと納税とネーミングライツ: 特定の避難路や公園の維持管理権を企業に販売し、企業のBCP(事業継続計画)やCSV活動としてインフラ維持に参加させる。
結論:変動を受け入れ、しなやかに残る
ローマの水道橋が2000年を経た今も人々を魅了し続けるのは、それが単に水を運ぶための管だったからではありません。風景と調和し、都市の誇りとなる「建築としての美学」を持っていたからです。
北海道、そして洞爺湖町のこれからの都市計画に必要なのは、自然を完全にコントロールしようとする「硬直的な工学」からの脱却です。ローマのような堅牢さを中心部に持ちつつ、変動する大地に対しては柔軟に形を変える「しなやかなインフラ」への転換が求められます。
「インフラとしての都市」を再構築すること。それは、人口減少と火山活動という二つの荒波の中で、私たちが人間らしい文化的な生活を維持するための、現代の城壁構築に他なりません。石を積み、道を敷くという原点に立ち返り、次世代に「負債」ではなく「資産」としてのインフラを残すことこそが、今を生きる私たちの責務なのです。
関連リンク
お問い合わせ・ご依頼
地域課題の解決をお手伝いします。
些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。