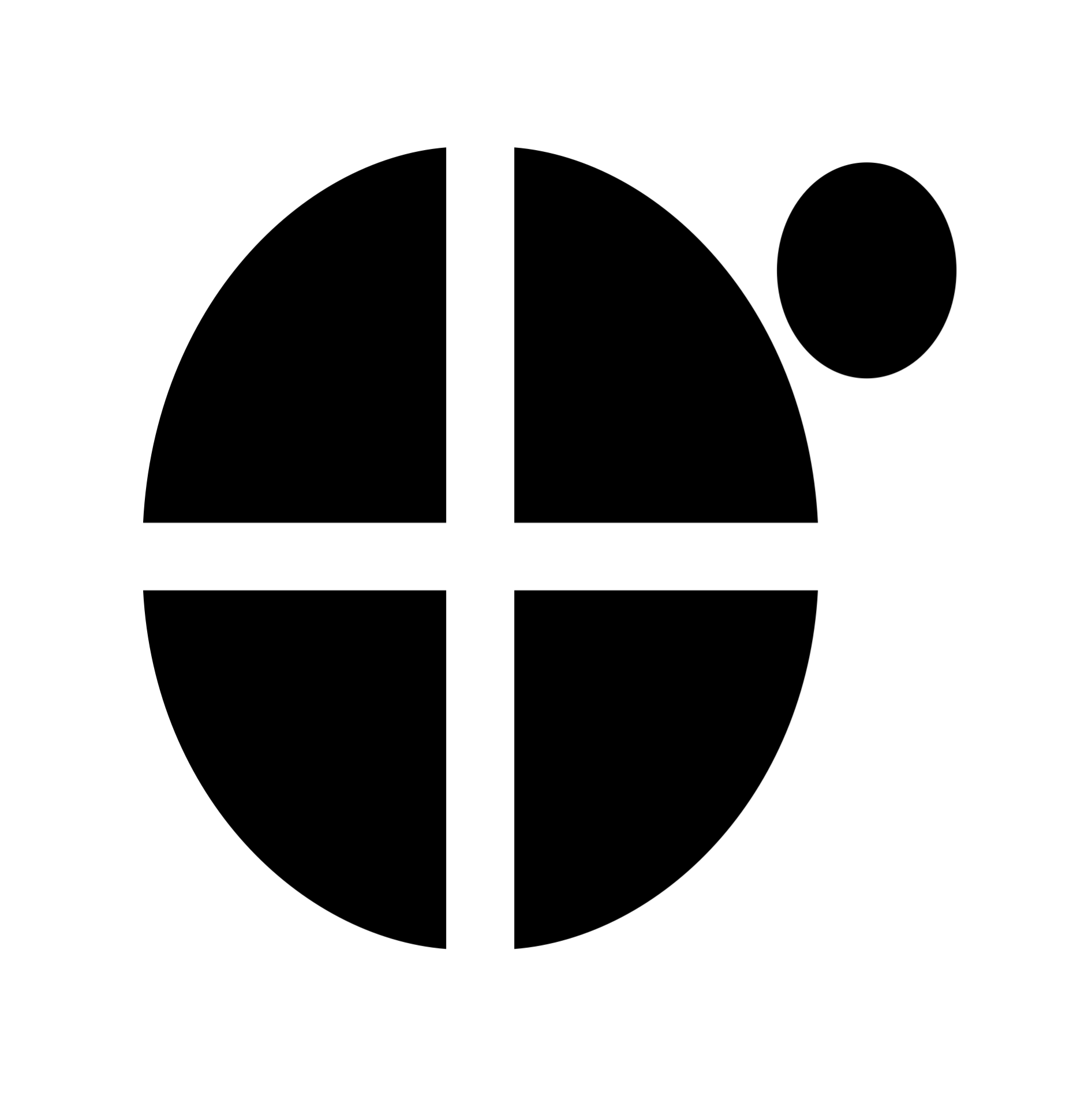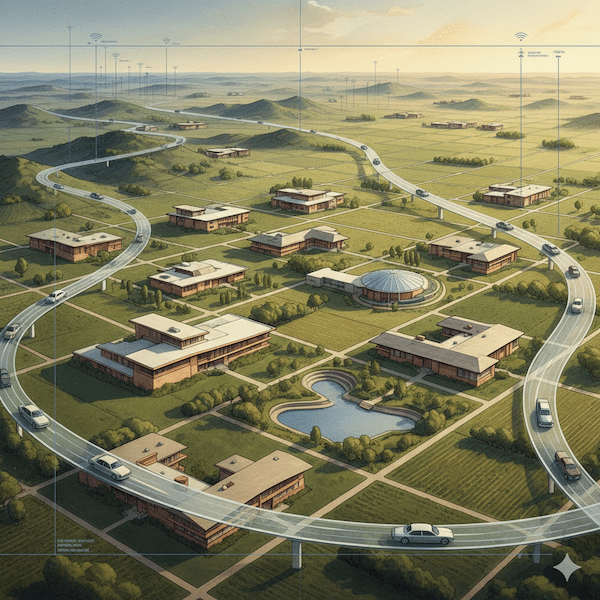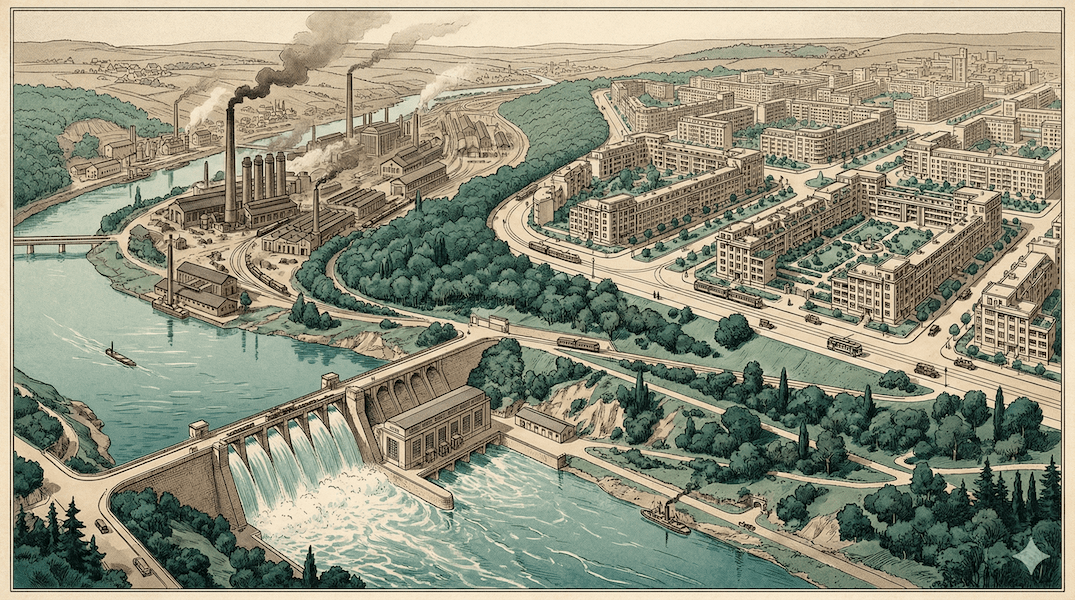〜「機能」と「芸術」の融合、そしてプレイスメイキングの新たな可能性〜
※本記事は2026年1月時点の統計・公開情報を基に構成しています。
私たちが普段、何気なく歩いている「街」という空間。その形状や広場の在り方が、実は100年以上前の「ある論争」の影響を色濃く受けていることをご存知でしょうか。
都市は、単なる「居住機械」であり、効率よく移動し生活するための機能的な装置に過ぎないのか。それとも、人々の記憶を紡ぎ、感情を揺さぶる「巨大な芸術作品」であるべきなのか――。この根源的な問いに対して、19世紀末のウィーンで、たった一人で近代合理主義の潮流に異を唱えた男がいました。彼の名はカミロ・ジッテ(Camillo Sitte)。
彼の著書『広場の造形(原題:芸術的原理に基づく都市計画)』は、定規とコンパスで引かれた無機質な都市計画に対する「人間性回復の宣言」として、現代の都市デザインにおいてもバイブルとされています。しかし、彼の理想とする「不規則で入り組んだ広場」は、現代日本、とりわけ積雪寒冷地である北海道においては、「除雪効率」という絶対的な正義の前に無力であるように思えます。
本稿では、あえてこの「ジッテの芸術論」と「北海道の過酷な現実」を衝突させます。札幌市の莫大な雪対策予算データや、洞爺湖町の観光投資の実態を紐解きながら、効率一辺倒のまちづくりからの脱却と、雪国における「美と機能の幸福な結婚(マリアージュ)」の可能性について、徹底的に掘り下げていきます。
1. 機能主義への抵抗:カミロ・ジッテの再発見と歴史的文脈
まず、時計の針を19世紀末のウィーンへと戻しましょう。なぜジッテは、当時の最先端であった都市計画に対して、これほどまでに激しい怒りと危機感を抱いたのでしょうか。その背景を知ることは、現代の私たちが直面している「画一的なまちづくり」の問題を理解する鍵となります。
「定規とコンパス」への反逆とリングシュトラーセ
1889年、ヨーロッパは産業革命の成熟期にあり、都市人口の爆発的な増加に対応するため、各地で大規模な都市改造が行われていました。その象徴が、ウィーンの城壁を取り払って建設された環状道路「リングシュトラーセ」です。
当時の技術者や為政者たちが目指したのは、「衛生」「通風」「交通の円滑化」でした。彼らは巨大な製図板の上で定規とコンパスを操り、幾何学的に完璧な左右対称(シンメトリー)の広場や、果てしなく続く直線のブールバード(大通り)を描きました。そこには、圧倒的な「秩序」と「権威」はありましたが、人間の身体感覚や心理的な安らぎへの配慮は欠落していました。
ジッテはこの状況を鋭く批判しました。
「現代の広場は、住民が集うための『サロン』ではなく、単に建物が建っていない『空地』に過ぎない。我々は定規で線を引くことには成功したが、居心地の良い空間を作る術を忘れてしまったのだ。広すぎる空間に対して、人々は不安を感じている。」
— カミロ・ジッテ『広場の造形』より意訳
なお、こうしたジッテの指摘は、後年の都市計画研究において「広場恐怖(アゴラフォビア)」の文脈とも結びつけて論じられています。
以下の地図は、ジッテが活動したウィーンの中心部です。リングシュトラーセ(環状道路)がいかに都市を大きく切り開き、巨大な空間を生み出したかが理解できます。ジッテは、この近代的なスケール感に対し、中世のヒューマンスケールを対置させたのです。
▼ウィーン:ジッテが批判と分析の対象としたリングシュトラーセ周辺
「屋根のない部屋」という比喩
ジッテが代案として提示したのは、中世やルネサンス期のイタリアの古都に見られる「不規則な美」でした。彼がヴェネツィアやシエナを歩き回り、スケッチを重ねて発見した法則は、現代の私たちにとっても新鮮な驚きを与えてくれます。
彼は広場を、家具の置かれた居室に例えるなど、都市における「屋根のない部屋」のような囲われた空間として論じました。室内において壁が重要であるのと同様に、広場においても「囲い込み(Enclosure)」が最も重要であると彼は説いたのです。四方が建物で適切に囲まれ、外部への視線の抜けが遮断されたとき初めて、人間は心理的な「守られている感覚」を覚え、そこに留まりたいと感じます。
ジッテ的モデルと、現代日本で一般的な機能主義的モデルの違いを、以下の表で詳細に比較します。この対比を見ると、なぜ日本の駅前広場が「ただ通り過ぎるだけの場所」になりがちなのか、その理由が見えてきます。
| 比較項目 | 【A】ジッテ的モデル (芸術的・中世都市の原理) |
【B】機能主義的モデル (近代的・日本の一般的都市) |
|---|---|---|
| 空間の定義 | 「屋根のない部屋」 生活と交流の舞台となる滞留空間。 壁(建物)による囲い込みを重視。 |
「交通結節点・空地」 駅前ロータリーや防災公園。 通過動線としての性格が強い。 |
| 街路形状 | 不規則・T字路 視線を制御し、絵画的な展開(シークエンス)を生む。 無限の遠近法を避ける。 |
グリッド(格子状)・直線 見通しの良さと区画整理の効率。 自動車交通の速度維持を最優先。 |
| モニュメント配置 | 偏心配置(オフセンター) 広場の隅や壁沿いに配置。 中央部は活動のために空けておく。 |
幾何学的中心 ロータリーの中央島など。 人が近づけない場所に象徴として置く。 |
| 空間の閉鎖性 | 高(Enclosed) 建物が連続し、隙間がない。 「守られた」感覚を生む。 |
低(Open/Leaky) 道路率が高く、建物が独立。 空間が四散し「漏れて」いる。 |
※表は横にスクロールできます
2. 北海道におけるジレンマ:雪とコストの壁
ジッテの理論は非常に魅力的です。「不規則な路地」や「中心を空けた広場」は、観光客に「この先には何があるのだろう?」という好奇心を抱かせ、滞在時間を延ばす効果があるからです。しかし、舞台をヨーロッパから北海道に移した瞬間、私たちは巨大な物理的障壁に直面します。それは「雪」です。
「美」と「除雪」の残酷なトレードオフ
北海道の都市計画、特に札幌や開拓期以降に整備された街区が「碁盤の目(グリッド)」を頑なに守り続けるのには、美学以上の切実な理由があります。直線道路こそが、大型除雪機械(グレーダーやロータリー車)を最も効率的に、かつ高速に稼働させることができる唯一の形状だからです。
もし、ジッテが推奨するように道路をあえて屈曲させ、広場の中に意図的な障害物(彫刻や植栽、ベンチ)を配置したらどうなるでしょうか。機械除雪のオペレーターは頻繁な切り返し(バック)を余儀なくされ、作業効率は劇的に低下します。それは即ち、維持管理費の高騰と、市民生活の麻痺を意味します。
この「機能維持のコスト」がいかに膨大か、札幌市のデータをグラフ化して見てみましょう。
【グラフ】札幌市の雪対策費総額の推移(合計)
出典:札幌市「雪対策予算」資料より作成
※グラフは横にスクロールできます
札幌市だけで年間約285億円(令和7年度案)。これは道路除雪やロードヒーティング等の維持管理を含む「雪対策費」の総額です。直線道路で効率化してもなお、これだけの予算が投入されています。ジッテ的な「不規則な美」を追求することは、このコストをさらに押し上げる要因となり得るのです。
一方で、洞爺湖町のような観光地では「効率」だけでは生き残れません。同町では広場整備やイルミネーション等の修景事業に、多額の投資を継続的に行っています。これは「見えないインフラ」だけでなく「見える風景」への投資が、経済を回すエンジンであることの証明です。
3. 洞爺湖町における実践:ジッテ理論の「雪国翻訳」
では、北海道においてジッテの理論は無用の長物なのでしょうか。いいえ、決してそうではありません。むしろ、「厳しい自然環境」と「観光地としての必然性」が交錯する洞爺湖町こそ、ジッテの理論を現代的かつ地域的に「翻訳」して適用する最適な実験場です。
洞爺湖町が直面する課題は、「広大な湖への眺望(Open)」と、ジッテが求める「守られた囲い込み(Enclosure)」のジレンマをどう解決するかという点にあります。
▼洞爺湖温泉街:湖畔に広がる線状の街区。ここにいかに「滞留性」を作るかが課題となる。
解法1:「光」による仮想的な囲い込み
物理的な建物で広場を囲んでしまうと、除雪の邪魔になる上に、せっかくの湖の景色が見えなくなります。そこで有効なのが、洞爺湖温泉街でも実践されている「イルミネーショントンネル」のようなアプローチです。
これはジッテが言う「屋根のない部屋」を、「光の天井」によって仮想的に作り出す試みと解釈できます。冬の夜、雪の壁とイルミネーションのアーチによって視界が適度に遮られることで、広大な屋外空間の中に、突如として親密な(Intimate)空間が出現します。これは、除雪動線を阻害せず、かつ心理的な「広場」を形成する、雪国ならではの極めてスマートな解決策です。
解法2:除雪を逆手に取った「可変型広場」
ジッテは「広場の中心は空けておくべきだ」と説きました(中心に記念碑を置くな、という意味です)。この教えは、北海道の冬において別の意味で機能的合理性を持ちます。
広場の中央を空けておけば、冬場はそこを「雪堆積場」兼「スノーパーク」として活用できるからです。夏はジッテ的な「不規則で美しい広場」としてビアガーデンやイベントに使い、冬はその広場全体を雪で埋め尽くして、かまくらや滑り台を作る。 「夏のアート(ジッテ的景観)」と「冬の機能(雪捨て場)」を同一空間で両立させるこの「可変性(Modifiability)」こそが、北海道のまちづくりにおける最強の武器となります。
4. 未来への展望:テクノロジーが補完する「中世の美」
最後に、これからのまちづくり技術が、ジッテの理想をどのように復活させるかについて触れておきましょう。デジタル技術の進化は、かつて機能主義によって否定された「不便だが美しい街」を、再び実現可能なものへと変えつつあります。
自動運転と「歩行者中心主義」の復権
自動運転技術(MaaS)の普及は、道路における「自動車のためのスペース」を劇的に圧縮する可能性があります。車線幅が狭くなれば、その分を歩行者のための「滞留空間」や「植栽帯」に転用できます。 かつてジッテが愛した、人間と馬車が共存していたようなヒューマンスケールの道路幅が、最先端技術によって逆説的に復活するのです。
AR/VRによる景観の補完
物理的に建物を建て替えなくても、AR(拡張現実)グラスを通すことで、広場の欠けた部分に「仮想の壁」や「歴史的なモニュメント」を出現させることが可能になります。 洞爺湖の何もない駐車場が、ARを通すと中世イタリアのような賑わいのある広場に見え、バーチャルな焚き火を囲んで人々が交流する――。そんな「情報空間におけるジッテ的広場」の創出は、すでに技術的には可能な未来です。
結論:機能主義の上に描く「手書きの揺らぎ」
カミロ・ジッテが1889年に発した問いかけは、100年以上の時を経て、現代の北海道において新たな意味を帯びています。
私たちは長い間、都市の「機能」を最適化することと、人間の「感情」を満たすことはトレードオフ(二律背反)だと信じ込まされてきました。札幌市の285億円にのぼる雪対策費は、確かに都市の生存を支える不可欠な基盤です。しかし、それだけでは人は集まらず、街への愛着(シビックプライド)も生まれません。
洞爺湖町が目指すべきは、機能主義を全否定することではありません。除雪や交通という生存のための屈強な「骨格(インフラ)」は維持しつつ、その上に、人々の感情を揺さぶるジッテ的な「皮膚(インターフェース)」をどう重ね合わせるか。
「定規で引いた線の上に、手書きの揺らぎを取り戻すこと」
これこそが、次世代の資本である「関係性」をデザインするための、最も戦略的なアプローチなのです。
関連リンク
- 国土交通省: 居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり(ウォーカブル推進施策)
- 洞爺湖町公式サイト: 洞爺湖町景観計画・ガイドライン
- 公益社団法人 日本都市計画学会: 都市空間の質的評価に関する研究論文集
お問い合わせ・ご依頼
地域課題の解決をお手伝いします。
些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。