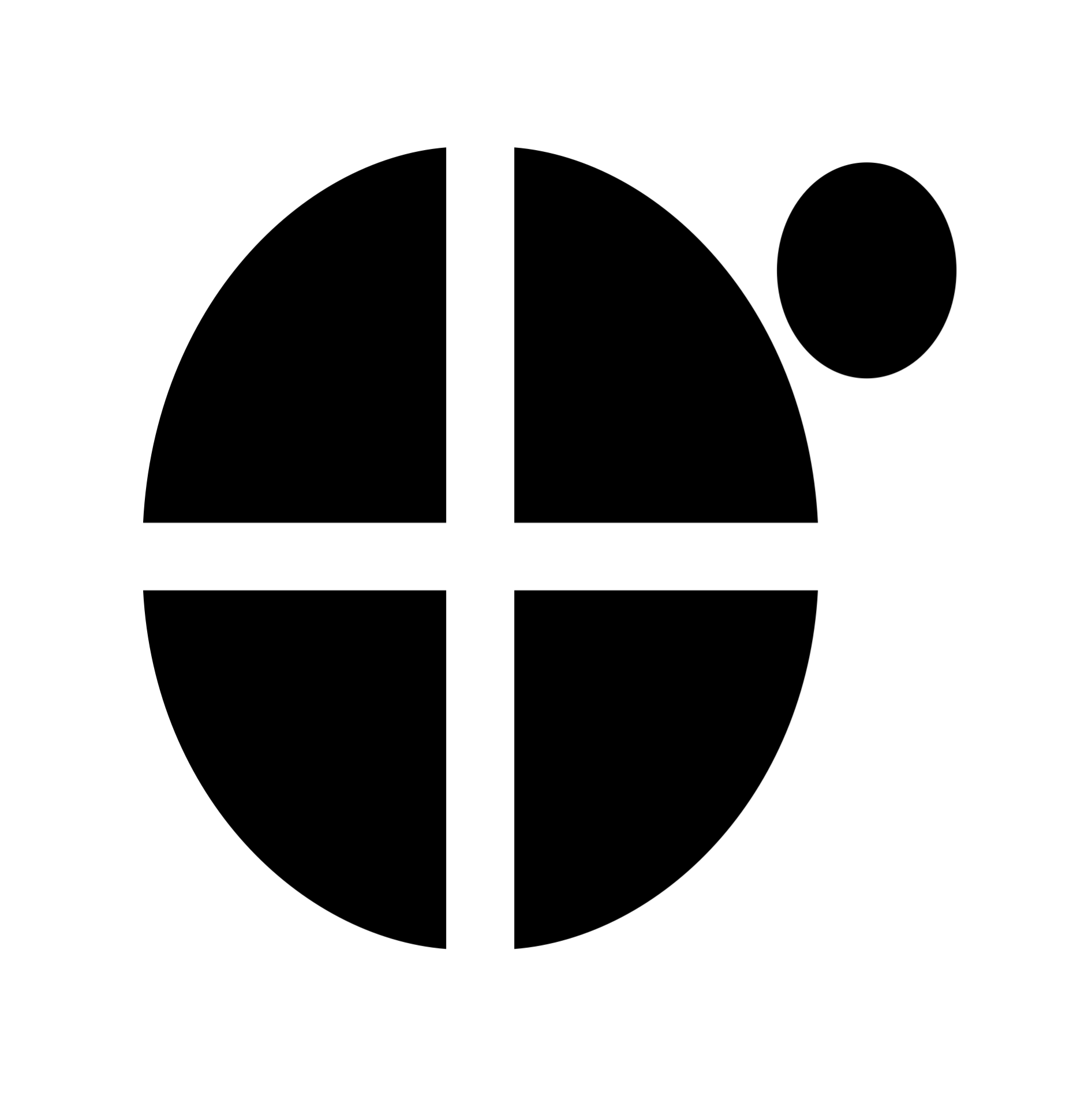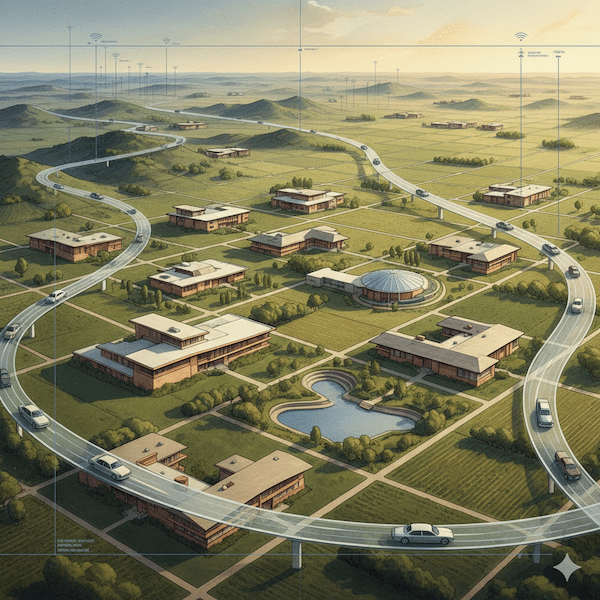〜災害を奇貨として導入された建築規制(コード)と受益者負担の仕組み〜
※本記事は2026年1月時点の情報を基に構成しています。
都市がその姿を劇的に変えるとき、そこには往々にして悲劇的な「破壊」が存在します。
すなわち、平時においては到底合意を得られないようなドラスティックな変革も、瓦礫の山という圧倒的な現実を前にして初めて、その実行力が正当化されるのです。その最も象徴的な事例こそが、17世紀の英国で発生した「ロンドンの大火(Great Fire of London)」に他なりません。
1666年9月、パン屋の竈(かまど)から始まった一筋の炎は、瞬く間に中世以来の木造都市を飲み込み、ロンドン市街の85%を灰燼に帰しました。しかし、都市計画の専門的な視座からこの出来事を俯瞰(ふかん)するとき、それは単なる災禍以上の意味を帯びてきます。
換言すれば、それは木造密集という脆弱なシステムから、煉瓦と石による「燃えない都市」へと、都市のOS(オペレーティングシステム)を強制的に、かつ不可逆的にアップデートした歴史的転換点だったのです。
本稿では、近代都市計画の原点とも言えるこの復興プロセスを、当時の法令やデータに基づき詳細に紐解きます。さらに、その知見を現代の日本、とりわけ「火山」という抗い難い自然の脅威と共に生きる北海道・洞爺湖町における「強靭なまちづくり」へと接続し、具体的な応用可能性を探ります。
1. 1666年、ロンドンはなぜ燃え尽きたのか
「薪の山」としての木造密集都市
まず、当時のロンドンが置かれていた状況を整理しましょう。17世紀中葉のロンドンは、貿易による繁栄の絶頂にある一方で、都市構造としては致命的な欠陥を抱えていました。
当時のロンドンを構成していたのは、タールを塗った木造家屋です。これらが迷路のような狭い路地に密集し、文字通り「薪の山」を形成していました。加えて、前年の1665年にはペスト(黒死病)が大流行しており、衛生環境の改善も待ったなしの状況でした。
特に被害を拡大させた構造的要因として、当時の一般的な建築様式である「ジェティ(Jetty)」が挙げられます。これは、建物の2階、3階部分が道路に向かってせり出す構造です。土地が狭いため、上層階の床面積を少しでも稼ごうとする庶民の知恵でしたが、これが防火上の悪夢となりました。
向かい合う家々の屋根は、通りを挟んで握手ができるほど接近していたと言われています。この構造が一種の「トンネル効果」を生み、炎は風に乗って容易に道路を飛び越え、次々と延焼していったのです。
▼ 大火の記念塔(The Monument)と出火地点プディング・レーン周辺
4日間の破滅的なタイムライン
1666年9月2日未明、プディング・レーン(Pudding Lane)にある王室御用達のパン屋、トマス・ファリナーの店から出火した炎は、瞬く間に東風に乗って市街地を飲み込みました。
サミュエル・ピープス(Samuel Pepys)の日記によれば、人々は消火活動よりも家財道具の持ち出しに奔走し、テムズ川は荷物を満載した小舟で埋め尽くされたといいます。当時の市長トマス・ブラッドワースの優柔不断な対応も災いし、初期消火の機会は失われました。
結果として、4日間にわたる火災により、以下の壊滅的な被害が発生しました。
📊 ロンドン大火の被害規模概算
※当時のロンドン人口の約1/6に相当
2. 「不燃化」か「空間確保」か。日英の復興思想比較
ロンドンと江戸、対照的な災害への回答
ここで視点を広げ、同時代の日本と比較してみましょう。奇しくもロンドン大火の9年前、1657年に日本の江戸でも「明暦の大火」が発生しています。世界最大級の二つの都市が、ほぼ同時期に壊滅的な火災に見舞われたのです。
興味深いのは、その後の復興アプローチの決定的な違いです。地震のリスクが低いロンドンは、重量のある不燃素材で都市を固める「抵抗(Resistance)」の道を選びました。対して、地震多発地帯である江戸は、燃えることを前提としつつ延焼を食い止める「回避(Avoidance)」の道を選びました。
この差異は、単なる建築材料の違いを超え、都市計画における「思想」の違いとして現代まで受け継がれています。
| 比較項目 | ロンドン大火 (1666) | 明暦の大火 (1657・江戸) |
|---|---|---|
| 基本戦略 |
不燃化 (Brickization) 都市全体を燃えない素材へ物理的に置換する「剛」のアプローチ。 |
延焼遮断 (Firebreaks) 火災の発生を許容し、空間によるバッファで食い止める「柔」のアプローチ。 |
| 主要建材 |
煉瓦・石造の義務化 ※木造外壁は厳格に禁止された。 |
木造の継続 ※土蔵造りも奨励されたが、コスト面から限定的であった。 |
| 都市空間 |
既存道路の拡幅・直線化 (キング・ストリートの新設など、物流効率も考慮) |
「広小路」や「火除地」の設置 (現在の上野広小路などがその名残) |
| 復興財源 |
石炭税 (Coal Tax) 港湾利用税による公共投資。受益者負担の原則。 |
幕府の御救金 および大名・町人の自己負担(自助・公助の混合)。 |
ロンドンの復興において特筆すべきは、「石炭税」という受益者負担の仕組みを導入した点です。公共建築や教会の再建費用を、ロンドン市民が日常的に暖房や調理で使用する石炭への課税で賄いました。これは、現代における都市計画税や目的税の先駆けとも言える先進的なシステムであり、財源確保のリアリズムにおいて江戸のそれを凌駕していたと言えるでしょう。
3. 近代建築規制の誕生:1667年再建法
「コード」が都市のデザインを決める
焼け野原となったロンドンに対し、クリストファー・レンやジョン・イヴリンといった当時の第一級の知識人たちは、パリやローマに倣った壮大なバロック様式の都市計画案を提案しました。幾何学的なグリッドと放射状の街路を持つ、理想的な都市図です。
しかし、現実にはこの理想案は実現しませんでした。その最大の理由は「権利関係の複雑さ」です。土地の境界をすべて引き直すには膨大な測量時間が必要であり、商業都市としての早期復興を望む市民や商人たちは、それを待てなかったのです。
その代わりに採用されたのが、1667年の「ロンドン再建法(Rebuilding of London Act)」でした。これは、既存の街路網(土地の区割り)を維持しつつ、建物の「質」と「規格」を厳格にコントロールするという、極めてプラグマティックな手法です。
📜 1667年再建法の主要ポイント
-
① 煉瓦・石造の完全義務化
すべての外壁を不燃材とすること。違反した建築物は強制的に取り壊された。 -
② 建物の等級化(Standardization)
道路の重要度に応じて建物を4つの等級に分類し、それぞれの「階数」と「壁の厚さ」を厳密に規定した。
・第1種(路地裏):2階建て
・第2種(通り):3階建て
・第3種(大通り):4階建て
・第4種(邸宅):4階建て(セットバックあり) -
③ ジェティ(張り出し)の禁止
上層階の突出を禁止し、垂直なファサードへ統一。これにより上空の延焼経路を遮断した。 -
④ 雨水処理の近代化
屋根の水を直接道路へ垂れ流すことを禁じ、縦樋(パイプ)の設置を義務化した。
中でも技術的に画期的だったのが「Party Wall(界壁)」の規定です。隣り合う建物が煉瓦の壁を共有し、その壁を屋根の上に突き出させる(パラペット)ことで、物理的に火の回りを遮断しました。
これは現代日本の建築基準法における「防火区画」や「界壁」の考え方と完全に一致しています。350年前のロンドンで、すでに現代の防災ロジックが法制化されていたという事実は、驚嘆に値します。
4. 強靭化の光と影:誰のための復興だったのか
秩序と安全の確立
煉瓦造への統一は、ロンドンに「恒久的な秩序」をもたらしました。火災リスクの劇的な低減は、投資家や外国商人に「ロンドンは安全な投資先である」という強いメッセージを与え、その後の世界金融センター「シティ・オブ・ロンドン」としての発展を下支えしました。
また、道路拡幅と下水設備の整備は、前年まで猛威を振るっていたペストなどの疫病の温床、すなわち不衛生な過密環境を一掃する副次的効果も生みました。「火災裁判所(Fire Court)」による迅速な権利調整も機能し、都市は驚異的なスピードで物理的な復興を遂げたのです。
排除(Gentrification)と均質化
一方で、復興のコストは甚大でした。高価な煉瓦建築を建てられない貧しい職人や労働者階級は、再建された都心部に住み続けることができず、規制の緩い郊外のイーストエンドへと追いやられました。これが現代に続く「ロンドン東側の貧困」の遠因とも言われています。
また、中世特有の有機的で雑多な街並みは失われ、規格化された赤煉瓦の壁が延々と続く風景に対し、当時は「単調で味気ない」「人間味がない」という批判も少なくありませんでした。安全と引き換えに、都市の多様性が削ぎ落とされた側面は否定できません。
5. 北海道・洞爺湖町における「現代の再建法」
「火」ではなく「火山」に備えるレジリエンス
さて、ここからは時計の針を現代に進め、場所を北海道・洞爺湖町に移しましょう。ここでの最大の脅威は、ロンドンや江戸のような「大火」だけではありません。20世紀だけで4回(1910, 1944, 1977, 2000年)も噴火した有珠山、そして厳しい冬の寒さと雪です。
ロンドンの事例から私たちが学ぶべきは、単なる煉瓦の模倣ではなく、「災害を前提とした都市の物理的スペックの再定義」という思想です。
▼ 洞爺湖温泉街と有珠山の位置関係
提言①:避難大通り(Evacuation Boulevard)の再定義
ロンドンが大火後に「キング・ストリート」や「クイーン・ストリート」を新設・拡幅したように、洞爺湖温泉街のメインストリートもまた、単なる観光道路ではなく「絶対的な避難路」として再定義する必要があります。
具体的には、建物の一部が倒壊したり、火山灰が積もったりした状況でも、大型の避難バスや緊急車両が双方向ですれ違える幅員(15m以上)を確保することです。しかし、ただ道を広げるだけでは街の賑わいが失われます。
そこで重要なのが「デュアルユース(二義性)」のデザインです。平時は広げた歩道をオープンカフェやイベント広場として活用し(江戸の広小路的機能)、有事には障害物を撤去して「命の道」とする。この柔軟性こそが、現代の強靭化の本質です。
提言②:北海道における「煉瓦」の復権と進化
建材についても再考の余地があります。北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)に象徴されるように、北海道にはかつて煉瓦建築の文化がありました。しかし、地震への弱さや凍害(内部結露による劣化)の問題から、現代では主流から外れています。
しかし、技術は進歩しています。構造体(骨組み)は耐震性の高いRC造やCLT(直交集成板)とし、外装のみを高品質な北海道産煉瓦で覆う「レインスクリーン工法」などを採用すれば、どうでしょうか。
これにより、ロンドンのような「重厚で燃えない、安心感のある街並み」という観光資源を作り出しつつ、現代の断熱性能と耐震性能を両立させることができます。空き家対策として、老朽化した木造建築を除却し、こうした「強靭な建築」への建て替えを誘導するガイドラインは、現代の洞爺湖における「再建法」となるはずです。
提言③:現代版「石炭税」としての観光目的税
最後に財源です。ロンドンは復興のために「石炭税」を導入しました。現代の観光地においてこれに相当するのは「宿泊税」や「入湯税」の拡充でしょう。
ただし、単なる徴収ではなく、使途を「強靭化(防災インフラ整備)」にすることが重要です。「あなたが支払った税金が、この街の電線を地中化し、避難路を整備しています」というメッセージは、観光客に対しても「安全なリゾート」というブランド価値として還元されるからです。
結論:規制こそが都市の寿命を決める
セント・ポール大聖堂の南扉には、建築家クリストファー・レンの墓碑銘と共に、ラテン語でこう刻まれています。
“Resurgam”(私は再び起き上がる)
1666年のロンドン市民は、焼け跡に安易なバラックを建てる道を選ばず、コストと痛みを伴う「煉瓦の都市」への転換を選びました。その厳格な「コード(規制)」への合意こそが、その後のロンドンの繁栄を決定づけたのです。
翻って現代の私たちも、人口減少や空き家問題、そして迫りくる自然災害に対し、目先のコスト効率だけでなく「100年後の風景」を見据えた意思決定ができるでしょうか。
壁の厚さ一枚、道路の幅一メートル。それらは単なる数値ではなく、その街が「生き残る」という強い意志の表れなのです。
関連リンク
- London Fire Brigade (LFB) – The Great Fire of London(ロンドン消防庁による公式記録)
- Parliament UK – The Rebuilding of London Act 1667(英国議会による再建法の解説)
- 気象庁 – 有珠山の火山活動解説(北海道の防災リスク背景)
お問い合わせ・ご依頼
地域課題の解決をお手伝いします。
些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。