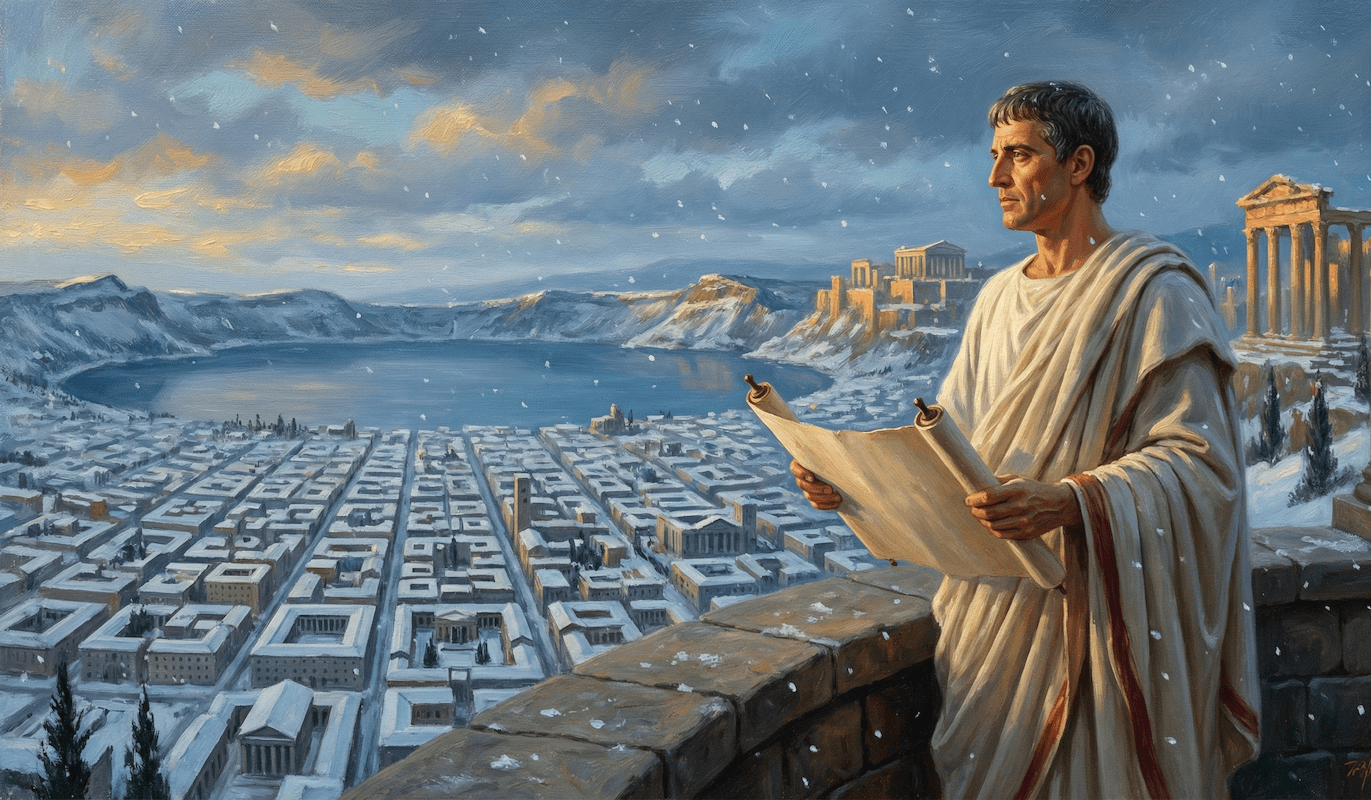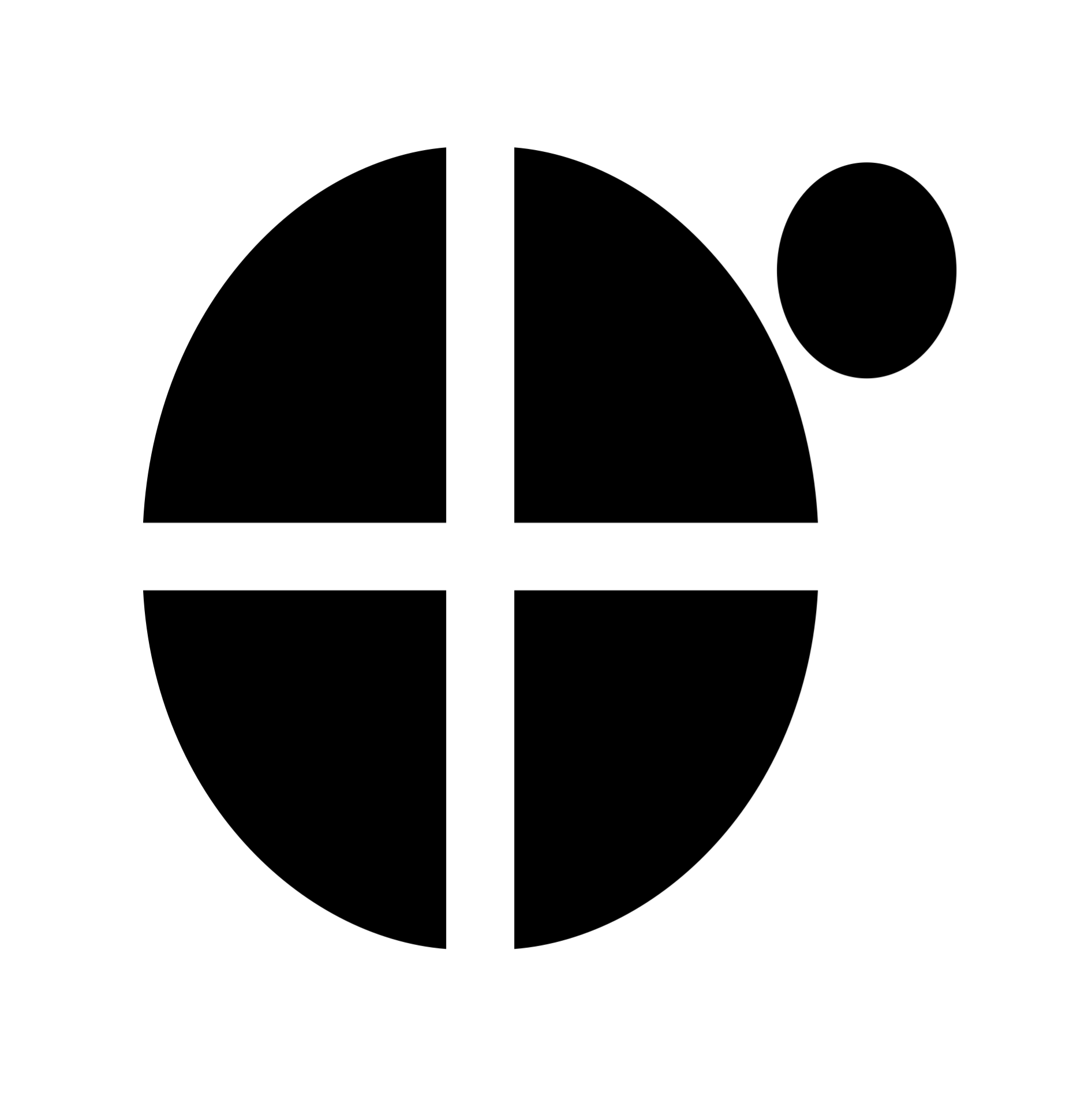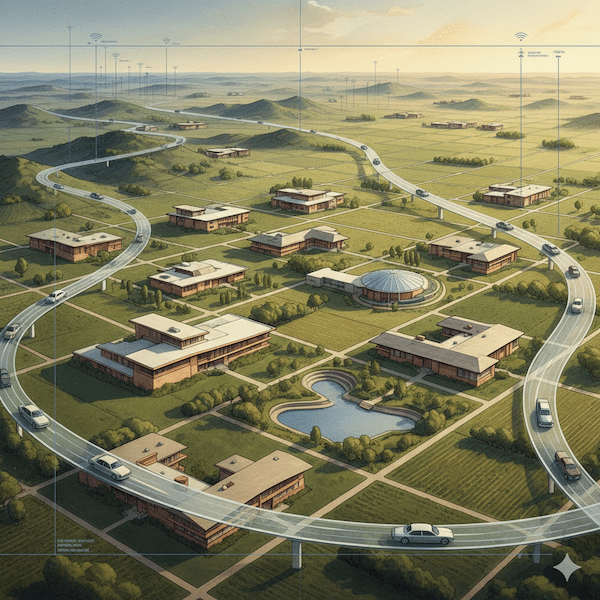〜古典的理想と、雪国・火山地帯という過酷な現実との対話から、現代都市が目指すべき「共生」の哲学を紐解く〜
※本記事は2025年12月時点の情報を基に構成しています。
もし仮に、2000年前のローマ帝国を生きた一人の建築家が、時空を超えて冬の北海道に降り立ったとしたら、彼は眼前に広がる光景に対して何と言うでしょうか。
おそらく、彼は札幌の街並みを見て、その幾何学的な美しさに一度は感嘆の声を上げるでしょう。整然と区画された碁盤の目、真っ直ぐに伸びる大通公園。それは、ローマ人が愛した理性の具現化そのものに見えるからです。
しかし、その直後、北西から吹き付ける猛烈な季節風に煽られ、彼は顔をしかめてこう叫ぶに違いありません。
「なぜ、わざわざ風の通り道を作るのだ! これでは都市そのものが巨大な風洞ではないか」と。
彼の名は、マルクス・ヴィトルウィウス・ポッリオ。現存する西洋最古の建築理論書『建築十書(De Architectura)』を著した人物です。彼が紀元前1世紀にアウグストゥス帝に捧げたこの書物は、都市計画の聖典として、ルネサンス期を経て現代に至るまで、建築家たちのバイブルであり続けています。特に彼が提唱した「強(Firmitas)・用(Utilitas)・美(Venustas)」の三原則は、あらゆるデザインの普遍的な評価軸となっています。
ところが、理論というものは常に、現実の過酷な環境と衝突し、変容を余儀なくされる運命にあります。イタリア半島の温暖な気候を前提としたヴィトルウィウスの理想は、極寒と豪雪、そして活火山と共生しなければならない北海道・洞爺湖町というフィールドにおいて、どのように適用され、あるいはどのように「創造的誤読」を経て進化しているのでしょうか。
本稿では、古代ローマの叡智を補助線としつつ、現代北国のまちづくり(Machizukuri)を多角的に比較・検証します。そこから見えてくるのは、単なる歴史の対比ではなく、人間がいかにして自然と対話し、生存領域を拡張してきたかという、壮大な「環境適応」のドラマです。
1. 風と街路の幾何学:逃げるローマ、対抗する北海道
都市を設計する際、最初に考慮すべきものは何でしょうか。土地の価格でしょうか、それとも交通の利便性でしょうか。ヴィトルウィウスの答えは、もっと根源的なものでした。それは「風」です。
ヴィトルウィウスの警告「風を招き入れるな」
ヴィトルウィウスは『建築十書』第1書第6章「街路の方位と風向きについて」において、都市計画の最初のステップとして、城壁内の街路区画(区割り)を行う際、「街路を風向きに対抗させてはならない」と強く主張しています。
彼の理論によれば、風とは「空気の流動する波」であり、その動きは目に見えないものの、都市の衛生環境を決定づける物理的な力です。もし、その土地の卓越風(最も頻繁に吹く風)の方向に正対して街路を設計してしまった場合、どうなるでしょうか。街路そのものが、物理学で言うところの「風洞(ウィンド・トンネル)」と化してしまいます。
遮るもののない直線道路を駆け抜ける風は、勢いを減衰させることなく都市の奥深くまで侵入します。ヴィトルウィウスは次のように警鐘を鳴らしました。
- 「冷たい風は不快であり、居住性を損なう。」
- 「熱い風は人々を衰弱させる。」
- 「湿った風は健康を害する。」
したがって、彼は街路の方向を、主要な風向きの「中間」に向けることを推奨しました。つまり、風が建物の角(街区の角)に当たるように配置することで、風の勢いを砕き、拡散させ、路地や家屋への直接的な吹き込みを防ぐという手法です。これは現代の環境工学で言うところの「パッシブデザイン(受動的な環境制御)」の先駆けと言えるでしょう。
彼は実際に、レスボス島のミティレネという都市を例に挙げ、その都市がいかに美しく壮大に建設されていても、配置計画において「配慮(prudentia)」を欠いていると批判しました。「南風が吹けば人々は病に倒れ、北西の風が吹けば咳き込み、北風が吹けば回復はするものの、激しい寒さのために街路や路地に立つことすらできない」という記述は、まるで現代の冬の札幌の光景を予言しているかのようです。
北海道が選んだ「雪」との戦いとトレードオフ
翻って、明治期以降に建設された北海道の主要都市、とりわけ札幌を見てみましょう。開拓使によって計画されたこの都市は、東西南北の方位(Cardinal Directions)に正確に基づいた、典型的なグリッド都市(碁盤の目)です。
ヴィトルウィウス的な視点から見れば、これは極めて「リスクの高い」配置です。なぜなら、北海道の冬の卓越風である北西の季節風に対して、直線的な街路が真正面から、あるいは斜めに長く続くことで、風速を維持したまま都市内へ寒気を引き込む構造になっているからです。
では、なぜ北海道の開拓者たちは、あえてこの構造を選んだのでしょうか。そこには、ヴィトルウィウスが想定しなかった、北国特有の変数が存在しました。それが「積雪」です。
北海道の都市計画において、冬期の最優先課題は「風の制御」ではなく、「交通機能の維持」、すなわち「除雪の効率性」でした。以下の表で、その対比を確認してみましょう。
| 比較視点 | 【ヴィトルウィウスの理論】 | 【北海道・札幌の現実】 |
|---|---|---|
| 街路の方位 | 風向きに対して斜め(Off-axis) 風を建物の角で砕き、勢いを拡散させることを重視。 |
東西南北に正対(Cardinal) 土地測量の容易さ、近代化の象徴としてのグリッドを重視。 |
| 優先順位 | 健康・居住性(シェルター機能) 屋外を歩く市民を風から守ることが最優先。 |
機能・効率(物流・排雪空間) 積雪期における都市機能の麻痺を防ぐことが最優先。 |
| 解決策 | 都市の「配置」そのもので風を避ける。 | 直線道路で「機械除雪」を可能にする。 地下空間や高断熱建築で風を防ぐ。 |
もし、ヴィトルウィウスの教え通りに、風よけのために路地を複雑に屈折させていたらどうなっていたでしょうか。現代の巨大な除雪車や排雪トラックはスムーズに運行できず、雪の捨て場(堆雪帯)の管理も困難を極めていたはずです。直線で見通しの良い道路は、雪国においてはライフライン維持のための必須条件だったのです。
その代わり、現代の都市は別の方法でヴィトルウィウス的な「シェルター」を実現しました。それが、地上の風を完全に遮断する「地下歩行空間(チ・カ・ホ)」の整備や、個々の建築物の断熱性能向上による「建築的防御」です。都市構造で風を受ける代わりに、技術の皮膜で人間を守る。これが北海道の出した回答でした。
図:都市計画における優先パラメータの比較
2. 美(Venustas)の管理:オーダーからマンセル値へ
次に、ヴィトルウィウスの三原則の一つ、「美(Venustas)」について考察します。現代において「美」とは主観的なものと捉えられがちですが、古代ローマにおいては、それは数学的で厳格なルールに基づくものでした。
ヴィトルウィウスにとっての「美」とは、個人の感性ではなく、客観的な「比率(エウリュトミー)」と「対称性(シンメトリー)」でした。
神殿の円柱の太さと高さ、柱間の距離、コーニスの張り出し具合。それら全てには、ドリス式、イオニア式、コリント式といった様式(オーダー)ごとに厳格な数学的定義が存在しました。このルールを守ることこそが都市の品格であり、市民に安心感を与える「秩序」であるとされたのです。
現代の洞爺湖町において、この「美の規律」は形を変え、「マンセル値」という数値管理として機能しています。
支笏洞爺国立公園を有するこの町では、個人の好みで建物を極彩色に塗ることは許されません。なぜなら、ここでは「自然景観」こそが主役であり、人工物はその背景に徹するべきだという、明確な美学が存在するからです。
「10YR 2/1」が守る風景の品格
具体的に、洞爺湖町の『景観ガイドライン』を見てみましょう。ここでは、建築物の外壁に使用できる色彩が、色相・明度・彩度を示すマンセル値によって極めて詳細に指定されています。
例えば、「10YR 2/1」のような、彩度の低い(鮮やかさを抑えた)色彩が推奨され、逆に赤や黄色といった高彩度の原色は、原則として使用を控えるよう求められます。これは、「目立つこと」を目的とする商業主義的な看板や建築に対し、公的な枠組みで「待った」をかける仕組みです。
一見すると、これは表現の自由に対する過度な制約に見えるかもしれません。しかし、ヴィトルウィウスが「神殿は街のどこからでも仰ぎ見られるべき威厳が必要だ」と説き、公共空間の秩序を重んじたのと同様に、洞爺湖町においては「羊蹄山」や「中島」、そして「湖面」そのものが、現代の神殿の役割を果たしています。
建築物の高さを制限し、色彩をアースカラー(大地の色)に統一することで、人間が作った都市が壮大な自然の一部として溶け込む。これこそが、現代における「美(Venustas)」の再定義であり、高度に知的なデザインコードの実践なのです。
3. 用(Utilitas)と強(Firmitas):循環と再生の都市論
最後に、都市の機能性「用(Utilitas)」と、構造的な強さ「強(Firmitas)」について、ローマと洞爺湖町の驚くべき共通点と相違点を探ります。
現代の水道橋:温泉集中管理システム
ローマ文明は、別名「水の文明」とも呼ばれます。ヴィトルウィウスは第8書を丸ごと水について費やし、水源の発見方法から水質の検査、そして長大な水道橋による供給システムについて詳述しました。特に鉛管による健康被害(鉛中毒)の可能性にまで言及し、陶管の使用を推奨するなど、その視点は医学的ですらありました。水というインフラの公平な分配こそが、都市の機能性(Utilitas)の根幹だからです。
現代の洞爺湖温泉では、この精神が「温泉集中管理配湯方式」として受け継がれています。かつて、高度経済成長期の観光ブームにおいて、各ホテルが競って個別に源泉を掘削し、水位低下や資源枯渇の危機に瀕した歴史がありました。この「共有地の悲劇」を防ぐため、町は源泉を一括管理し、巨大なパイプラインを通じて各施設へ「熱水」を配給するシステムを構築しました。
さらに、現代の技術はローマの理想を超えています。『洞爺湖町上水道事業経営戦略』などの資料によれば、使用済みの温泉排水からヒートポンプを用いて熱エネルギーを回収し、再利用する仕組みまで導入されています。資源を一度きりで使い捨てにせず、徹底的に循環させる。これは、古代の知恵を現代の環境倫理(サステナビリティ)でアップデートした姿と言えるでしょう。
強さとは「壊れないこと」ではなく「立ち直ること」
そして、「強(Firmitas)」の概念における決定的な違いが、ここ洞爺湖町には存在します。
ヴィトルウィウスは、建築の基礎を堅固な地盤に置き、恒久的な石材やレンガを用いることで、数百年にわたって変わらない「永遠の都市」を目指しました。彼にとって、変動する土地(沼地や軟弱地盤)は避けるべきリスクでしかありませんでした。
しかし、洞爺湖町は活火山・有珠山の麓にあります。ここでは数十年おき(20世紀だけでも1910年、1944年、1977年、2000年)に噴火が起き、大地そのものが隆起し、形を変えます。どんなに強固な石積みも、マグマの圧倒的な力の前では無力です。
この不可避な運命に対し、洞爺湖町が示した回答は、世界でも類を見ないものでした。それが「災害遺構の保存」です。
- 破壊された公営住宅をそのまま残す。
- 隆起した道路や折れ曲がった線路を遊歩道として整備する。
- 廃墟から植物が芽吹く様子を「再生の象徴」として見せる。
これは、自然を征服し管理しようとしたローマ的価値観からの、劇的な転換です。「災害は防げない」という前提に立ち、破壊された記憶すらも都市のアイデンティティ(資産)として組み込む。洞爺湖有珠山ジオパークの理念でもある「変動する大地との共生」は、頑強さ(Robustness)ではなく、しなやかな回復力(Resilience)こそが、現代における真の「強さ」であることを私たちに教えてくれます。
結論:対話としての都市計画
ヴィトルウィウスの『建築十書』から2000年。コンクリートや鉄骨、デジタル技術によって都市の姿は劇的に変わりましたが、私たちが直面している課題の本質は、驚くほど変わっていません。
それは、「人間は、圧倒的な自然の力とどう折り合いをつけて生きるか」という根源的な問いです。
風を避けるために道を曲げることを選んだローマ人と、雪をのけるために道を直角にすることを選んだ札幌市民。永遠を求めて石を積んだ古代人と、循環を受け入れて噴火跡と共に生きることを選んだ洞爺湖町民。そのアプローチは正反対に見えますが、その根底に流れているのは、自分たちが住む土地の「声(風、雪、熱、地殻変動)」を聴き、その制約の中で最適な解を導き出そうとする、人間ならではの真摯な知性です。
私たちが現代のビジネスや生活の中で「持続可能性(サステナビリティ)」を語るとき、単なるスローガンではなく、この洞爺湖町のまちづくりが示しているような、「自然への畏敬」と「工学的合理性」のギリギリのバランス感覚こそが、大きな示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
ヴィトルウィウスもまた、もし現代の洞爺湖を訪れたなら、その「強・用・美」の新しい解釈に、満足げに頷くのかもしれません。
関連リンク
お問い合わせ・ご依頼
地域課題の解決をお手伝いします。
些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。